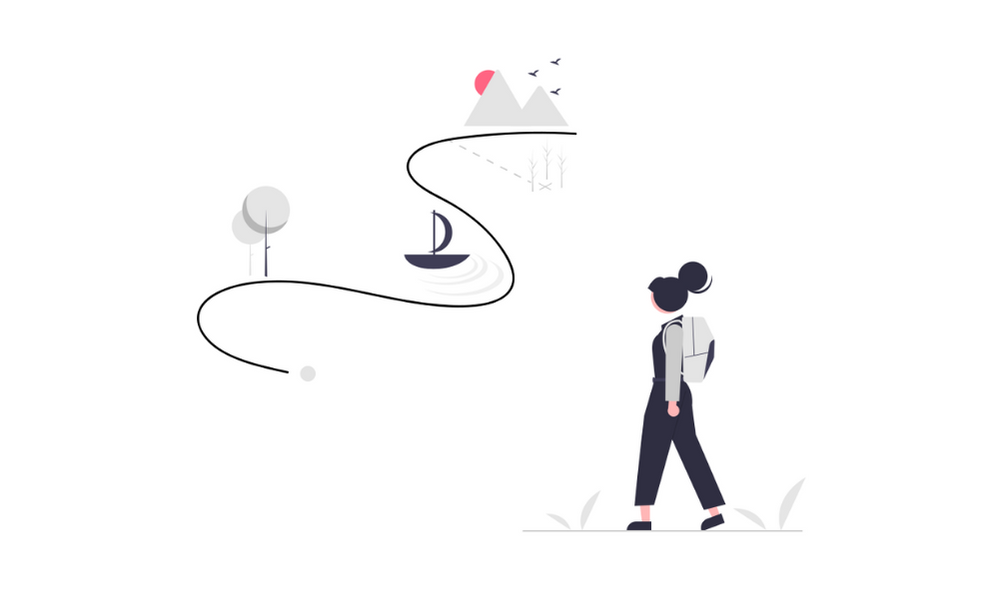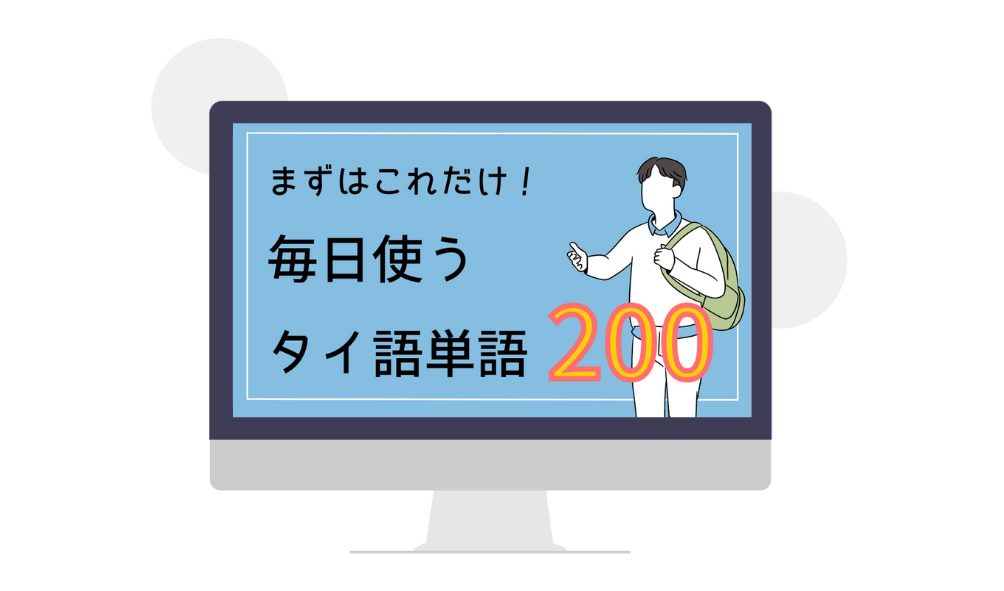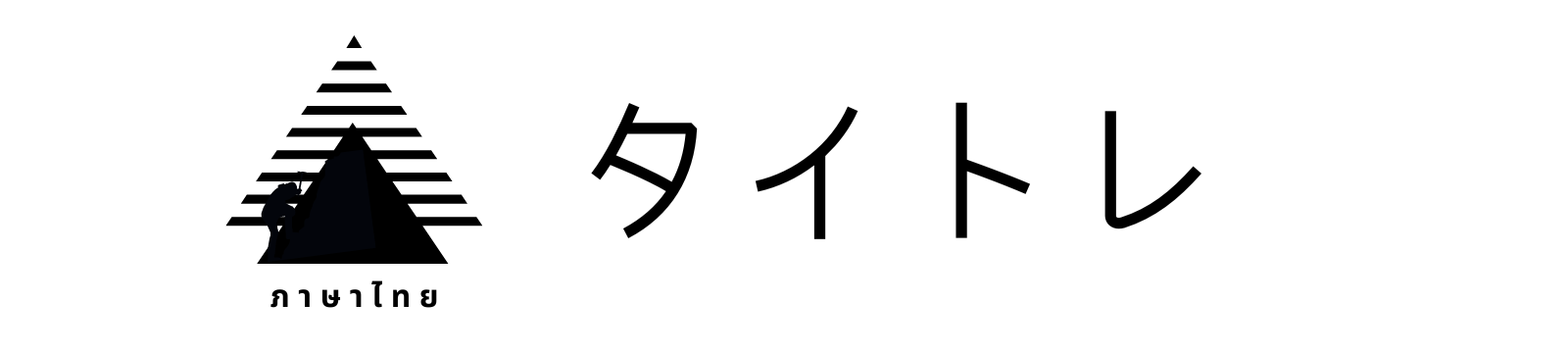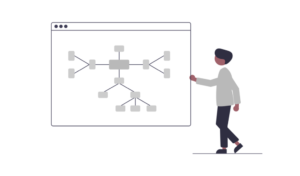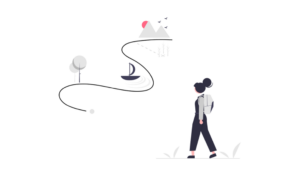こんにちは、けいです。
僕は長文読解パートが苦手で試験全体の得点を下げるお荷物的存在でした。
ですが今回紹介する解き方に変えたことによって、準2級の試験では読解パートを全問正解することができました。
今回は長文が苦手な方向けに、僕が実際に行った長文問題の解き方やコツを紹介します。
長文読解問題の解き方

読解問題を解く流れについては以下の通りです。
- 本文を読む
- 問題文・選択肢を読む
- 本文に戻り、答えを探す
- 最後に答えを記入
今回は1~4の中で最も重要なポイントである1.本文を読むと2 .問題文・選択肢を読むのやり方を詳しく説明していきます。
本文を読む
まず始めに問題文を読むのではなく、いきなり本文から読み始めます。
人によっては問題文から読むという方もいらっしゃると思います。
僕も問題文を読んでから本文を読むスタイルでしたが、話の大筋がわかっていない状態なので、あまり効果がないと感じていました。
そこでおもいきって本文から読むようにすると、うまく解けるようになりました。
では次に本文を読む際にどのような点に気をつけていくかを説明していきます。
ポイント1 キーセンテンスを探す
本文を読む上で大切なのは話の大筋を掴むことです。
そのためにはキーセンテンスとなる文章を探しながら読んでいきます。
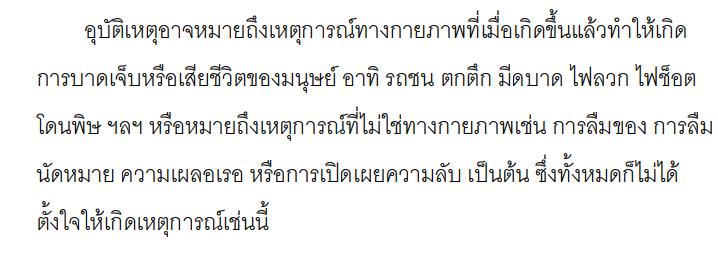
事故とは身体に外傷を負う。
または、人が命を落とすことを意味する。
例えば、車にはねられる、ビルからの落下、切り傷、火傷、感電、中毒などがある。
もしくは身体に影響を及ぼさないもの。
例えば、忘れ物、約束を忘れる、うっかりする、秘密を漏らすなど。
すべて意識して起こしたものではない。
赤い文字のところがキーセンテンスです。
キーセンテンスは段落の1行目や最後の行にあることが多いので、段落の読み始めや終わりは特に意識して読むようにしてください。
また、キーセンテンスに下線を引いて読んでいくこともおすすめします。
問題文を読んだあとで「どこだっけ?」ということを防ぐことができます。
接続語に注目する
接続語は以下のようなものです。
- または
- 例えば
- もしくは
- 要するに
- しかし
- なので
接続語にも印をつけながら読むと本文の理解が深まります。
先ほどの例文では、
- または
- もしくは
- 例えば
が接続語となります。
また、接続語に気を付けることで、キーセンテンスの見落としに気づくこともできます。
簡単な文で説明すると、
トムヤムクンは唐辛子を入れる。
しかし、それだけではおいしくならない。
ココナッツミルクを入れることによっておいしくなる。
「トムヤムクンは唐辛子を入れる」というキーセンテンスを掴んだつもりになったとしても、「しかし」という接続語に注意できなければ、後ろにある「ココナッツミルクを入れることによっておいしくなる」というもうひとつのキーセンテンスにも気づくことができません。
例に挙げた文は短いので、キーセンテンスが二つあることはすぐにわかりますが、実際の長文問題では気がつきにくいので、接続語に注意を払いながら、キーセンテンスを探してください。
問題文・選択肢を読む
本文を読んだら次は問題文と選択肢を読みます。
問題文・選択肢を読むときに気を付けることを以下の通りです。
- 問題・選択肢をしっかり最後まで読む
- 読んで分からなかった場合は適当に答えて先に進む
選択肢をしっかり最後まで読む
基本的なことですが、問題・選択肢をしっかり最後まで読むことを心がけてください。
問題文が「ひっかけ問題」の場合や「当てはまらないものはどれか」という問題の場合もあります。
また、タイ語検定は4択ですが、稀に、1択がすべて当てはまるという選択肢のパターンもあります。
例えば、先ほど例に挙げた長文でこのような問題があったとします。
Q:外的損傷は以下のうちどれか?
- 切り傷
- 火傷
- 感電
- すべて当てはまる
この場合、4が正解です。
しかし、問題を最後まで読まなければ、1を選んで次に進んでいる可能性があります。
上記では日本語で書いたので、1~4全体を瞬時に見て判断できますが、タイ語で書かれていると、視野が狭くなり4を見落とす可能性があります。
こういったことも起こりうるので、問題文と選択肢はしっかりと最後まで読みましょう。
読んで分からなかった場合は適当に答えて先に進む
選択肢を読んでどうしてもわからない場合は適当に解答して、先に進むのをおすすめします。
タイ語検定は時間との勝負でもあるので、問題文や選択肢の意味が分からない場合は、そこで時間を割くよりも、ほかの問題を解いたり、見直したりすることをおすすめします。
なんとなく一番ありそうな選択肢を選ぶか、事前に選ぶ数字を決めておいてもいいかもしれません。
僕は数字の「3」が好きなので、全く分からない問題に会ったときは、「3」を選んでさっさと次の問題に進みました。
長文問題を解くために必要な能力
上記では長文問題の解き方を紹介しましたが、解き方やテクニックに頼るのには限界があります。
まずは自力をつける必要があります。
長文問題を解けるようになるために必要な能力は以下の2つです。
- 語彙力
- 長文に慣れる
語彙力
長文は文の集まりです。そして、文は単語が集まって出来ています。
長文読解の解き方でわからない単語は推測するとありましたが、前後の文や単語がわからなければできません。
極力わからない単語は減らす必要があります。
そのためには単語帳や長文を読んで、たくさんの単語に出会い、それらを覚えていくことが必要です。
長文に慣れる
これも長文問題を解けるようになるために大事なことです。
文を日頃から読んでおくことで、文の流れ・文の構成を知ったり、長い文を読むときにかかるストレスに慣れておきます。
継続的に続けていくと、だんだんと頭の中でタイ語から日本語に変換せずに、タイ語のままで読めるようになってきます。
これができるようになれば時間的にも余裕が生まれるので、文を読むときはこのことも意識して読んでみてください。
継続的に文を読むには
継続的に文を読むには、文を読む行為を習慣化していくのが一番です。
そのアイデアとして、『Twitterで勉強する』『タイ語の本で読書する』といった勉強法を当ブログでは紹介しています。
興味のある方はこちらも読んでみてください👇
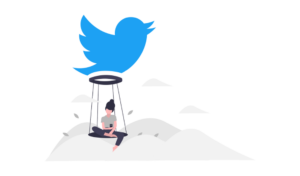

まとめ
今回は長文読解問題の解き方や対策についてご紹介しました。
もういちどまとめると
長文問題を解く手順
- 本文を読む
ポイント:キーセンテンスと接続語を探す。 - 問題文・選択肢を読む
ポイント:最後までしっかり読む - 本文に戻り、答えを探す
- 最後に答えを記入
長文問題を解くために必要な能力
- 語彙力
- 文に慣れる
今回は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございます。